
ヨウ素(ヨード)不足にならないように、毎日、飲み水にヨード液(ヨウ素を含むビタミン剤の類を含む)を1滴入れる飼い主さんがいるようですが、絶対にやめてください。ごく微量、1滴の1/4の量をセキセイインコの幼鳥に1年半毎日与えた結果、発育不全など健康上の問題が生じて、中には亡くなってしまうケースもあったと、1970年代に学術的な報告がされています(※1)。
1950年代から70年代にかけて、セキセイインコの甲状腺腫について行われた諸々の生体実験を基に、ドイツのクロンベルガー教授は、毎日ヨウ素を与えると有害になるとして、ヨウ素欠乏の予防として与える場合は、週に1回とされています(※2)。また、日本初の小鳥専門病院を開業し、日本の小鳥医療に大きく貢献された高橋達志郎先生も、週に2回とされています(※3)。毎日与えろ、などとする専門家は最初からいなかったのです。
つまり、1日1滴必ずヨード液を与えるのは有害で、そもそも有り得ない行為と言えます。この点、人間での話となりますが、厚生労働省は過剰摂取を回避すべきものとして、ヨウ素を位置づけ日常的にヨウ素を過剰摂取した場合、甲状腺機能低下や甲状腺腫になってしまうと、明確に指摘しています(※4)。
したがって、もし、かかりつけの獣医さんに、特に病気の治療目的ではなく、ヨウ素欠乏の予防のためだけのために、1日1滴必ずヨード液を与えるように指示を受けても、従ってはいけません。飼い主の手で我が子(飼鳥)に毒となるのがわかっている行為をして加害者にならないでください。
ヨウ素は、小鳥にとっても必須のミネラルですが、穀物飼料と水道水や水耕栽培の野菜(豆苗)には、ほとんど含まれていません。そのため、他に海産物の類を与える機会がない場合は、特に成鳥となった後に、ヨウ素欠乏により甲状腺腫となるリスクが高まります。ただ、人の場合の推定平均必要量は100μg(0.1mg)に過ぎず、人の体重の1/2000程度の文鳥では、推定平均必要量も0.05μg(0.00005mg)程度となって、極、ごくごくごく極微量、ボレー粉でも1回なめる程度で欠乏症を防げると思われます(※5)。
そもそもヨウ素欠乏は、飲み水がヨウ素などのミネラルを多く含めば起きず、ミネラル分が少なければ起きることがある、といった微妙なもので、こうすればこうなると決まっているような単純なものではありません。蒸留水のみで飲水からヨウ素が摂れなくしても、甲状腺変化を起こさなかった、とする実験結果もありますが(※6)、そもそも、代々20代繁殖して数十羽飼育する飼育経験の中で、私は「苦しそうにあえぎ、ヒューヒューと妙な声を連続的に発」する甲状腺腫に特徴的に起きる症状を見たことがありません。私が信用できないとしても、私が甚だよろしくないと思っている鳥小屋で大量に繁殖する江戸時代から続く繁殖環境でさえ、「ヒューヒュー」は指摘されていません。また、大雑把な展示をしているだけの昔の小鳥屋さんで売られていた文鳥が、「ヒューヒュー」もだえている姿も見たことがありますか?私は…、数羽の疑い例はあっても、並んでみんな「ヒューヒュー」している惨状の記憶はありません。それが現実です。つまり、何も気を付けなくても、運動不足の環境では起きにくく、大いに運動する環境でも、普通の飼料で補えるのがヨウ素、です(※6)。
「甲状腺腫はセキセイインコに著しく、死亡原因の2番目に多く」「報告は少ないですが、ブンチョウにも著しく多く、その発生頻度はセキセイを上回る可能性があります」と2010年にお書きになっている獣医さんがいますが(※7)、常識的にあり得ません。「報告は少ない」とするように、その獣医さんの動物病院でだけ起きている特殊現象と考えるのが妥当で、誤った認識による毎日のヨウ素摂取による過剰症の疑いが濃厚です。その動物病院に患者の小鳥たちが、その獣医さんの指導の下で毎日飲み水にヨウ素を添加しているのなら、過剰の実例としてのみ理解できる現象だからです。
以上、ヨウ素は必要な栄養素ですが、必要量はごくわずかで、人工的に飲み水に添加すれば過剰が起きやすく、昔から毎日の添加は厳禁とされていること、それを理解していない臨床医が危険な処方をしていることが有り得ることを、ご理解いただけたでしょうか。
本来は、心配なら穀物飼料に少しボレー粉を混ぜておくだけで済む話です。水浴びしたり飛びまわったり、十分な運動をしても問題ない栄養の摂取を、過剰の危険をしないで、補っていきたいですね!
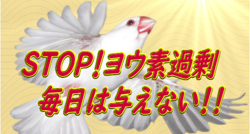
当然ながらリンクフリーです。バナーを使う人がいるなら、テキトーに縮小して使え・・・、でいいんですけど、よろしければ→でもご利用ください。
※1 ドイツのクロンベルガー教授の著書『鳥の飼育と疾病』(学窓社より日本語訳本が1980年に刊行されている。現在は国立国会図書館によりデジタル資料化され公開されている)に、「飲料水0.5㍑に対しヨード水5滴」を1年半与えたところ、「飼育した幼鳥で翼羽、尾羽のない鳥、いわゆる跳躍や走れない鳥が目立った。これらの鳥は発育不全で、若干のものは死亡した。組織学的には、正常活性または軽度障害の甲状腺が見られた」とある。 重要部分のスキャン画像はこちら参照
※2 『鳥の飼育と疾病』P150 (予防として)「週に1回30mlの飲料水にルゴール溶液1滴入れて与えてもよい」とある。
※3 1962年日本初の小鳥専門病院を開業され臨床医として多くの小鳥の治療に当たられた高橋達志郎先生の一般向けのご著書『小鳥の飼い方と病気』(永岡書店 知る限り1990年刊行とするものと1994年刊行すとするものがある)には、「25ccの飲み水の中に一滴たらし、毎日新しくかえて三週間連続投与し、その後一週に二回ぐらい投与する日を決め、他の日は普通の飲み水を与えます」とある。
※4 厚生労働省が2015年より5年ごとに更新している「日本人の食事摂取基準」では、ヨウ素の項目に「過剰摂取の回避」(2025年版P315-316)として「日常的にヨウ素を過剰摂取すると、甲状腺でのヨウ素の有機化反応が阻害されるが、甲状腺へのヨウ素輸送が低下する“脱出(escape)”現象が起こり、甲状腺ホルモンの生成量は基準範囲に維持される。しかし、脱出現象が長期にわたれば、甲状腺ホルモンの合成に必要なヨウ素が不足するために甲状腺ホルモン合成量は低下し、軽度の場合には甲状腺機能低下、重度の場合には甲状腺腫が発生する」と、説明されている。
※5 カキ殻を飼料に加工している鳥羽市開発公社は、製品内のヨウ素含有量を数値10gあたり49ppmとしている。100gでは490ppmで1mg=1000ppmとするなら、0.49mg、約0.5mgと考えられる(あまりにも少量なので、厳密に考えても現実的ではないが議論のためあえて行っている)。
1994年『AVIAN MEDICINE』による「オウム目、スズメ目飼鳥に推奨される飼料100gあたりの栄養含有量」は、ヨード0.03mgとしているらしい(横浜小鳥の病院の参考ページ)。食性の異なる多くの鳥類を同じ数値とするような大雑把なデータを、どのように決めたのか不明なので、参考にするのも不適当に思うが、あえてこれを基にして、文鳥が1日に食べる量を5~10gとすれば、0.0015~0.003mgのヨウ素を1日に摂取するように求めていることになる。これは、人の推定平均必要量から体重比で割りだした数値0.00005mgの数十倍に当たる異常なもので、これを基準にするのは、はなはだ危険と言わねばならない。
2006年コンパニオンバード誌上に、「ボレー粉から必要なヨードをすべて摂取するには、毎日0.5g以上食べなければなりません」と、一臨床医が根拠を示さず断じているのは、おそらく「オウム目、スズメ目飼鳥に推奨される飼料100gあたりの栄養含有量」を基にしての机上計算と思われるが、元とする数字が異常なので結論も誤りとせざるを得ない。科学的根拠が十分に存在する人体での研究を基にすれば、約0.5mg/100gのヨウ素を含むボレー粉のみで必要量0.0005mgをまかなえば良いのなら、ボレー粉1gに0.005mgなので、0.01gのボレー粉で足りる。これは指の先ほどの微量だ。
代々20代の文鳥その他を数十羽飼育する個人的な経験で言うなら、そもそも、日常的には別に置いたボレー粉はほとんど食べないが、繁殖期の特にメスは抱え込むようにしてボレー粉を食べる。我が家の場合、飼料にボレー粉を少々まぜているにもかかわらず、だ。これは、ボレーに含まれるカルシウムやヨウ素などのミネラルが大量に必要になるからで、その必要量の急激な変化を人工飼料や薬剤などで飼い主が調整するのは至難と思われる。
なお、アワ・ヒエ・キビ・カナリアシードなどの穀物飼料に添加した場合、逆にカルシウムなどの過剰を心配する意見が、1970年代頃にはあったようだが(『鳥の飼育と疾病』P53「(貝殻を飼料に添加すると)カルシウム過剰、吸収障害と腎障害を起こすことがある」)、カルシウムは経口摂取で過剰を起こしにくい栄養素なので、とりあえず考えなくて良いかと思う(問題になるのはビタミンDを配合してカルシウムの吸収を促進させているサプリメントの過剰摂取)。少しボレー粉をエサに混ぜてヨウ素を安全に補い、繁殖などの際はボレー粉を別置して好きなだけ食べられるようにする、ようするに我が家のいつもどおり、言われなくても多くの飼い主が実践している方法が、実際の飼育においては、結局無難な方法ではないかと思える。
※6 『鳥の飼育と疾病』には「半年間以上、飲料水として蒸留水のみを与えても、甲状腺変化を起こさなかった」とある。また、「セキセイインコの飼育には、水中に含有するヨードが元来関係を持つ。各地方の相異なったヨード含有量が、セキセイインコでも甲状腺肥大に種々の相違を示す。鳥小屋で鳥がよく運動すると、狭い鳥かごの中よりもさらに多くの水とそれに伴ったヨード摂取を必要とする。したがって鳥かごの中ではヨード不足となる。しかしセキセイインコはある程度のヨード欠乏に耐えることができる。さらにヨードが不足すると、たちまち甲状腺肥大となる」ともあり(P150)。さまざまな実験に矛盾するようなものも多かったと見なせる。
※7 小嶋篤史『コンパニオンバードの病気百科』(2010年誠文堂新光社)P136。なお、同著ではゴイトロゲンを含むだけで、「甲状腺腫が起きやすい個体や種では、アブラナ科(キャベツ、コマツナなど)の野菜は避け」るように書いているが、何のエビデンスも示していない。ゴイトロゲンについては、大量に摂取すると甲状腺がヨウ素を取り込むのを抑制してしまう作用がある、という実験結果だけであり、通常の摂取ではごく少量なので、人体にせよマウスにせよ、健康に異常をきたさないこともわかっている。鳥に対して特殊な薬理効果を示す科学的データは管見の限り存在しない。例えばコアラはほとんどユーカリだけを食べる生き物だが、ユーカリは猛毒の青酸化合物などの毒素を含んだ植物である。コアラからユーカリを奪えば、彼らは絶滅する。そのように、毒素があってもそれに順応するのが動物である。昔からアブラナ科植物を食性に取り入れている生き物に対し、生体実験などのエビデンスも用意せず、与えてはならないとするのは非科学的以上に非常識と言わねばならない。


コメント
超人和露易斯第二季高清完整版,海外华人可免费观看最新热播剧集。