
ゴールデンウィークの宿泊客たちが帰って行った。コザクラインコが別々の家から2羽いて、「ペケキョー!」と鳴くというか叫ぶと、ふたりで返事してくれるのでかわいらしかったが、疲れた・・・。
そのような中、行きがかり上、『日本人の食事摂取基準』2025年版のヨウ素の部分だけ読んでいた。この中でヨウ素の記載は微量ミネラルのところにあり、「過剰摂取の回避」として「日常的にヨウ素を過剰摂取すると、甲状腺でのヨウ素の有機化反応が阻害されるが、甲状腺へのヨウ素輸送が低下する“脱出(escape)”現象が起こり、甲状腺ホルモンの生成量は基準範囲に維持される。しかし、脱出現象が長期にわたれば、甲状腺ホルモンの合成に必要なヨウ素が不足するために甲状腺ホルモン合成量は低下し、軽度の場合には甲状腺機能低下、重度の場合には甲状腺腫が発生する」と説明されている。良かったね、ヨウ素欠乏が起きるメカニズムの説明が好きな獣医さんは、過剰の方のメカニズムも覚えておけば、二倍の能書きが言えるだろう。
メカニズムなど知らなくても、前世紀の70年代には動物実験でわかっていることで、何を半世紀後にやっているのかと、鼻で笑われないように、鳥専門などと言いながら過剰症になるような処方をしているか、した、臨床医の皆様には、ご精進いただくか、黙って頂きたいものである。
ゴイトロゲンについても、栄養学者の皆様のご見解が書かれている。「大豆製品の多食はヨウ素の体内利用や生体影響を減じる」とあって、アブラナ科の野菜ではなく、大豆のそれも大量に摂取した場合を問題視している。・・・、皆様ご存知かと思うが、一部の獣医が「処方食」と称して売っているハリソンのペレットも、かなり大豆を含んでいるようだ。テキトーに原材料表記をネット上から抜き取ってくると以下だそうだ。
「トウモロコシ、 ハダカムギ、 皮付アワ、 炒り大豆、 エンドウ豆、 レンズ豆、 ピーナッツ、 ひまわりの種、 挽き割り炒りオーツ麦、 アルファルファ、 玄米、 チアシード、 炭酸カルシウム、 ベントナイト、 混合トコフェロール(ビタミンE供給源)、 昆布、 食塩、 藻類、・・・以下略」
なんかいろいろ混ぜてくれている。昆布も入っているな。たぶんヨウ素の給源だが・・・、一方で大豆だ。有名なイソフラボンがゴイトロゲンの一種で・・・。大変だね、ヨウ素を入れたり抑制する物質が多かったり。
何で、一番ナチュラルな穀物原料を飼料にするのを嫌って、わざわざ人工物を与えておきながら、オーガニックを誇るのか、私にはまるでつじつまが合わないのだが、これだけは言える。文鳥でペレットを利用している人などごくわずかで、『文鳥屋』さんも売れないので取り扱いをやめたほどだ。もちろん宿泊者でペレットを与える人も稀(感覚的には1割未満)で、その中の1割くらいが元気で、9割はやたらとおとなしい・・・。食の多様性がない点が大きいのではなかろうか。しっかり考えたいものだ。
↑はウチのネズちゃんだが、生気にあふれ、いたずらそうな目つきで、結構なことである。

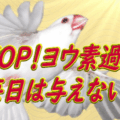
コメント