さて、事件はこれだけでは済まない。後日談も『吾妻鏡』から追ってみよう。
妻の妊娠期間中にこっそり昔からの愛人を近くに呼び寄せるなど、鎌倉幕府を開いた大人物にしてはつつましいものだし、妻は妻で、言われるまで気づかないくらい本当はのんきなものだったのだが、牧宗親の暗躍によって騒動が大きくなり、ただでは済まなくなってしまう。まずは天網恢恢、天罰が張本人の牧宗親に下される。
『吾妻鏡』1182年11月12日の記事(我流現代語訳)
頼朝様は気晴らしの遠出をされると称されて、亀前たちが逃れている大多和義久の鐙摺の家に行かれた。その一行に牧宗親も呼び出してお加えになった。そして鐙摺に到着すると、伏見広綱を呼び出され、一昨日の事件の顛末をお尋ねになられた。広綱は事細かにご報告する。そんなわけで打ちこわしの当事者である宗親もその場に呼ばれ、双方で議論させたところ、宗親は何も言うことが出来ず、ただ顔を地面にすりつけるばかりであった。その様子をご覧になった頼朝様はあまりに腹立たしかったので、自らの手で宗親の髻(もとどり、束ねた髪)をお切りになられた。その間宗親には「御台所(政子のこと)を尊重するというのは全く感心なことだ。しかし、その命令に従うのは当然としても、こんな場合に、どうしてこっそりと俺に知らせないのか。すぐに(俺の愛人に)恥ずかしい思いをさせたその考え方が、全くもって奇怪至極で許せん」と言い聞かされた。髻を切られた宗親は泣きながら逃亡してしまった。頼朝様はそのまま鐙摺の家にお泊まりになられた。
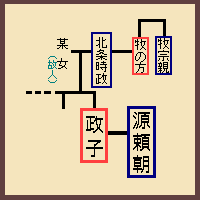 この部分は本当は原文の方が全然感じが出る。対決の場での牧宗親の様子は「陳謝舌を巻き、面を泥沙に垂る」だし、それ自体論理性が怪しい頼朝の言葉も、「ただしかの御命に順うといえども、此くの如き事は、内々になんぞ告げ申さざる哉。忽ちもって恥辱を与えるの條、所存の企て甚だもって奇怪」の方が読んでいて面白い。
この部分は本当は原文の方が全然感じが出る。対決の場での牧宗親の様子は「陳謝舌を巻き、面を泥沙に垂る」だし、それ自体論理性が怪しい頼朝の言葉も、「ただしかの御命に順うといえども、此くの如き事は、内々になんぞ告げ申さざる哉。忽ちもって恥辱を与えるの條、所存の企て甚だもって奇怪」の方が読んでいて面白い。
それはともかく、引き出され詰問されたであろう宗親は、実際には「舌を巻いて」黙ってなどいないで、「御台所様のご命令」を繰り返したものと思う。そうでなければ、後の頼朝の『説諭』(もしくは自分の不倫を棚に上げた言い逃れのへ理屈)が唐突過ぎるし、自分で家臣の髷を切ってしまうほど激怒したのも理解しがたいものになってしまう。前近代の日本人にとって、髻を切られるというのはまさに死ぬほど恥ずかしいことで、家来に対してもそのような罰を与えるなど、普通では考えられないことなのだ。
積極的な宗親の主体的な所業(おそらく「御台所様のご命令」を盾に、嬉々として家を壊していたものと思われる〉は被害者の広綱の証言で明らかであったはずなのに、すべてを政子の命令で言い逃れようとする小面憎さに、思わず堪忍袋がプッツリと切れてしまったのであろう。現代人はやたらと『キレル』らしいが、十数年も流罪地で写経などしていた源頼朝という人物は、本来とても自制心に富んでいたはずなのだ。
宗親としては政子の命令に従っただけといっておけば大丈夫だと思い、処分(というよりつるし上げのリンチ)を受けるなどとは思いもせずにノコノコついていったのだろう。ところが、頼朝の方は事件の原因が十分わかっていて、はじめから宗親を懲らしめるつもりだったのだ。さすが頼朝、なかなか手が込んでいる。
 事件後、それも一日置いて、そ知らぬ顔で張本人を呼び寄せて鎌倉の外に連れ出した頼朝は実に芸が細かく、事を荒立てないための配慮がうかがえる。しかし、はなはだ遺憾なことに、事はそれだけでは収まらなかった。
事件後、それも一日置いて、そ知らぬ顔で張本人を呼び寄せて鎌倉の外に連れ出した頼朝は実に芸が細かく、事を荒立てないための配慮がうかがえる。しかし、はなはだ遺憾なことに、事はそれだけでは収まらなかった。
11月14日、頼朝が鎌倉に戻ってくると、今度はへそを曲げてしまった北条時政(政子の実父〉が、鎌倉から本拠地の伊豆に帰ってしまったのである。
時政にとって牧宗親は妻の兄、つまり義理の兄弟だから、それに婿の頼朝が勝手にリンチを加えたのが面白くなかったのだろう。それに妻の手前、黙っているわけにはいかないではないか。
こうなると頼朝は困ってしまう。関東地方を中心とする武士階級の人々の支持を受けて鎌倉に本拠を据え、地方政権を構築してはいたが(西日本に平家、北陸方面に木曽義仲、東北に奥州藤原氏の勢力が別に存在)、つい二年前まで罪人として伊豆に軟禁されていた頼朝には、直属の軍事力は存在せず、頼りになる血族もいなかった。つまり妻政子の実家である北条氏こそ頼朝がもっとも信頼出来る勢力だったのだ。そこでさすがに苦労人の彼は妥協する。『吾妻鏡』によれば、時政の行動に腹がたってしかたがなかったが、時政の嫡男(政子の弟)が残っていたので呼び寄せて、
「理不尽なオヤジといっしょに行動しないで、おまえは偉い。本当に頼りになる。表彰したい。」
といった具合に褒めちぎったりしている。北条氏を頼りにしていることを間接的に伝えて、早く時政と手打ちをはかりたかったわけ。実に気を働かせる独裁者ではないか。
その後どのような交渉が有ったかは『吾妻鏡』には記されていないが、12月10日、政子の怒りを恐れる亀前を、頼朝がくどいてまた小坪の小中太の家に連れだし、16日に政子の怒りによって伏見広綱が遠江(現在の静岡県西部)に流罪となったといった記事が見られる。すべて「政子の怒り」をキーワードにしていて、何やら政子を軸に処分が決められていった印象を受けるが、このような記事の表現など、額面どおりには受け取れるものではない。何しろ怒りがあるはずなのに、結局愛人は小坪に戻っているわけだし、怒りがあるはずなのに、近くに「流罪」なのだ。
大体、広綱は頼朝の右筆となる以前(といってもこの年の五月)は遠江国の掛川に住んでいたとあるから、何の事はない実家に戻っただけなのである。つまり、この処分は頼朝と時政双方の面目を保つための妥協であって、政子の関知するところではないのが真相であろう。
さて、長々長と事件経過を見てきたが、頼朝の不倫そのものは、それほど問題ではなかったことには気づいていただけたのではないだろうか。亀の前が小坪に戻った後、一般に信じられているイメージとは異なり、政子が嫉妬で発狂した様子はないのである。何しろ当時は文字どおり「不倫は文化だ」ったのだ。京都の貴族社会で主流であった「妻問婚」は、『源氏物語』の光源氏のように複数の女性の家に男が通うという婚姻形態(その女性たるや、十二単に超ロングヘアーを引きずり歩き実質身動き不可能な存在だったので、ちょうどミノムシのメスが、木にぶら下がった巣の中でオスが来るのを待っているのを私は連想してしまう)だったし、やはり今にしてみれば、とんでもないスケベジジイである光源氏の行きつく果ての、複数の妻との同居というのも不思議ではなかった。実際に頼朝の父親も複数の妻を持っていたし、一応正妻を尊重すれば、妻が何人いようと、後ろ指さされる筋合いではなかった。
ただし、良く指摘される点だが政子の側の婚姻感は少し違う。彼女は伊豆の小豪族北条氏の娘、ぐんと庶民的なこの階層の人々は、基本的に一夫一妻制。しかもこの武士社会では女性も相続権を持つ分配相続を原則としたので、その結婚は嫁ぐというより、夫の資産と妻の資産の合併による一家の創設という趣が強かった。俄然女性も主体的に行動し、夫が死ねば、後家となった妻が一家の切り盛りをする。夫婦はいわば対等な共同経営者だったのだ。
となれば、夫が愛人を囲う程度なら許せても、自分と同等の妻を作るような行為は絶対に許されないのである。それでは共同経営が崩れ、一家が成立しなくなるのだ。つまり政子としてみれば、愛人は問題ないが、頼朝の妻は自分一人でなければならないのである。
こうした文化的に違う政子の心情は、苦労人の頼朝もわかっていたから、はじめは割合遠慮がちに夜遊びしていたのだ。ところが、調子に乗って、うっかり越えてはならない一線を越えてしまった。小岬一つ隔てただけだが、鎌倉の外である小坪に置いておけば良かったのに、わざわざ市中に新築したりするから正妻一族である北条氏の猜疑心(自分の立場が崩れる)をよぶ余地を作り、牧宗親などという人物に振り回される結果となったのである。
「不倫は文化だ。・・・・・しかし・・・ちょっと図に乗ったのがまずかった・・・かなあ。」
源頼朝は独りつぶやいたに違いない。
お終い
前のページへ
表紙に戻る
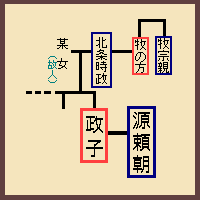 この部分は本当は原文の方が全然感じが出る。対決の場での牧宗親の様子は「陳謝舌を巻き、面を泥沙に垂る」だし、それ自体論理性が怪しい頼朝の言葉も、「ただしかの御命に順うといえども、此くの如き事は、内々になんぞ告げ申さざる哉。忽ちもって恥辱を与えるの條、所存の企て甚だもって奇怪」の方が読んでいて面白い。
この部分は本当は原文の方が全然感じが出る。対決の場での牧宗親の様子は「陳謝舌を巻き、面を泥沙に垂る」だし、それ自体論理性が怪しい頼朝の言葉も、「ただしかの御命に順うといえども、此くの如き事は、内々になんぞ告げ申さざる哉。忽ちもって恥辱を与えるの條、所存の企て甚だもって奇怪」の方が読んでいて面白い。 事件後、それも一日置いて、そ知らぬ顔で張本人を呼び寄せて鎌倉の外に連れ出した頼朝は実に芸が細かく、事を荒立てないための配慮がうかがえる。しかし、はなはだ遺憾なことに、事はそれだけでは収まらなかった。
事件後、それも一日置いて、そ知らぬ顔で張本人を呼び寄せて鎌倉の外に連れ出した頼朝は実に芸が細かく、事を荒立てないための配慮がうかがえる。しかし、はなはだ遺憾なことに、事はそれだけでは収まらなかった。