そこで疑いのフィルターを通して、『吾妻鏡』の弘長元年(1261)4月25日の記事を見なおすと、初めの筋立てから無理があるのに気づく。小笠懸をしたら、みんな下手だったので10歳の若君をお呼びする。それも父親の御推薦・・・。その頃の武士は武芸を日課にしており、しかも射芸の競技に出てくる連中は飛びきりの腕利き、いくら小笠懸が廃れてきているといっても出来ないはずはない
のだ。それに、ここではすっかり親馬鹿になっている時頼も、本当は冷静沈着で智謀に優れた人物だから、突如子供の自慢を始めるというのは実に不自然極まりないではないか。
どうもすべてが、時宗を登場させるための演技のように思えてくる。小笠懸をおこない、みんなが失敗し、若君時宗を呼び寄せ、みんなでその射芸を称揚する。儀式のようなものだ。
「いやまったく、大人の出来ない事を、やすやすと。さすが北条家のお世継ぎ。」
そんな筋書きが用意されていたのではないだろうか。弓が引けるまでに成長した嫡子のお披露目を華々しくおこなおうという趣向だ。もちろん時宗には、ずいぶん前から小笠懸の練習を十分に積ませておく・・・。
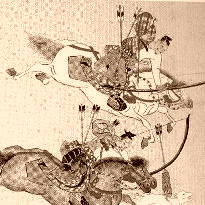 そもそも、わざわざ廃れ気味の小笠懸であるところにも意味がありそうだ。普通の笠懸は馬を疾走させながら、弓手(
馬の進行方向左側)にある的を射ぬく競技であるのに対し、小笠懸は馬手(右側)の至近にある的を射倒す競技だ。自分で馬に乗り、弓をつがえる動作を想像すればわかるが、右利きであれば左真横のものは射やすいが、右側面のものを射ることは出来ない。それでも右側でかろうじて可能なのは、馬の首のすぐ右横から弓の引き手に窮屈な思いをしつつ、矢を放つことが出来るが、この方法を競技化したのが小笠懸なのだ。
そもそも、わざわざ廃れ気味の小笠懸であるところにも意味がありそうだ。普通の笠懸は馬を疾走させながら、弓手(
馬の進行方向左側)にある的を射ぬく競技であるのに対し、小笠懸は馬手(右側)の至近にある的を射倒す競技だ。自分で馬に乗り、弓をつがえる動作を想像すればわかるが、右利きであれば左真横のものは射やすいが、右側面のものを射ることは出来ない。それでも右側でかろうじて可能なのは、馬の首のすぐ右横から弓の引き手に窮屈な思いをしつつ、矢を放つことが出来るが、この方法を競技化したのが小笠懸なのだ。
確かに大人が小笠懸をするのは難しそうだ。しかし、時宗は10歳の少年。体は小さいし柔らかいはずだから、大人の男よりもはるかに馬の首の右横からの騎射は楽だったに相違ない。
実は前例もある。建久元年(1190)4月11日、源頼朝が嫡男の頼家に小笠懸を行わせている。当時の頼家にいたっては満8歳足らずだ。
有力な御家人や一族をたくみに滅ぼし、幕府の象徴である将軍さえもすげ替え、得宗と呼ばれる北条氏嫡流の独裁体制を確立した大政治家の時頼なら、頼家の故事を引いてこの程度の演出は造作もないだろう。また、派手なセレモニーをして時宗を後継者として印象付けるのは、後で家督相続などを起こさないための予防策
にもなり、十分政治的な意味もある。
お膳立てが完全に整った出来レース、いわば回答をすべて教えてもらった上で受ける試験。これが時宗の小笠懸の内実だったので
はなかろうか。ところがよくよく記事を読むと、それでも少年時宗は失敗している。乗馬をうまく制御することが出来ずにまごついてしまうのだ。
記事によれば、遠笠懸に慣れた馬なので的の前を通りすぎてしまい、それを制御するために時宗が矢を射ることが出来ずにいるので、父親の時頼がアドバイスして、ようやく成功にこぎつけ
ることになっている。これを冷静に見れば、颯爽としているなどとはお世辞にも言えない。
さて、さらに細かく晴れ舞台における時宗少年の動きを考える上で、笠懸について少し説明しておこう。
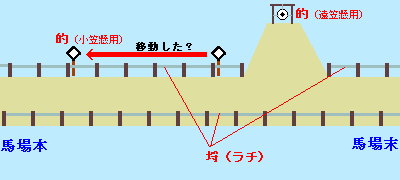 通常の笠懸(遠笠懸)は図のような舞台設定で行われる。馬場元から馬場末にかけて馬を疾走させ、弓手(左側)の中ほどの埒(ラチ)を開いて十数メ―トル離れたところに設置した的を射る。これに対して小笠懸は、馬場末から馬を逆走させつつ、埒際に低く立てた的を前のめり気味に射るものであるという(『国史大辞典』「笠懸」の項による)。
通常の笠懸(遠笠懸)は図のような舞台設定で行われる。馬場元から馬場末にかけて馬を疾走させ、弓手(左側)の中ほどの埒(ラチ)を開いて十数メ―トル離れたところに設置した的を射る。これに対して小笠懸は、馬場末から馬を逆走させつつ、埒際に低く立てた的を前のめり気味に射るものであるという(『国史大辞典』「笠懸」の項による)。
遠笠懸に慣れた鬼鴾毛(オニトキゲ、赤みのさした白色という珍しい毛色の馬)がいつもどおりに馬場を疾走してしまうのはわかるが、時宗が的前で止めようとする行動は何を意味するのだろうか。馬を走らせながら射倒すのが芸ではないのか
・・・。
さらに実行されることになる時頼のアドバイス、『的を通りすぎてから射る』、というのも不思議な話だ。馬手(右側)の的を通りすぎてから射るというのは人体の構造上不可能なのだ。つまりこの「的」というのは遠笠懸用の的の事で、いつもとは逆走ながら馬は的を通りすぎるとスピードを落とすので、小笠懸用の的をより馬場本に近い埒際にしつらい直せという意味と解釈する以外になさそうだ。
ようするにこの場面での少年時宗は、せいぜい並足程度の低速で的に近づいて的を射たものと思われる。疾駆する馬上で風圧を受けながら態勢を保つのは難しいに相違ないが、並足以下で目の前の的を射るのなら、現在の温泉場に見られる射的より容易であろう。考えてみれば、頼家は8歳足らずで行っているのだから、この小笠懸は、あくまでも少年用の儀式としての『小笠懸』に過ぎなかったと
見なした方が適当といえよう。
こうして考えていくと、時宗には同情せずにはいられない。父親以下の大人がお膳立てをしてくれた舞台で手間取っただけでも恥ずかしいのに、誰でも出来るようなほとんど静止した目の前の的を射当てただけで、周囲の大人が拍手喝さい。これでは赤ん坊が立ち上がるのを見て、両親
やらじいさんばあさんが大騒ぎするのと同じではないか。
「やあ、当てた、当たった、当てられた。すごい!すごい!!」
これでは当人の自尊心はいたく傷ついたに違いない。穴があったら入りたい。黙ってきびすを返すと、あいさつもしないで帰ってしまった気持ちもわかるではないか(この態度を生意気とする研究者すらいる)。・・・、かくして10歳にして心的外傷を受けた時宗は、笠懸が大嫌いになってしまったとすれば、翌々年の仮病もうなづけるではないか。
さて、後一つ問題が残っている。なぜ小笠懸で未熟をさらけ出してしまった時宗の一部始終を見ていた父時頼が、それでも自分の後継ぎにふさわしいなどといったのか。
これについても、時宗少年の行動をふりかえれば理解できるような気がする。周囲の言葉に従い一所懸命に練習し、本番ではうまくいかなかったが、投げ出すことなく何とか成功させようと悪戦苦闘、助言があると素直に従い目的を達成するが、それがあまりにも容易なことだったので、かえって周囲の誉めようとする反応を恥ずかしく思って、黙って帰ってしまう。
この中には、ひたむきなまじめさと、自分の行動を批判的に見つめられる目と、それに対する誠実な態度があるといったら、無理に誉めているようだが、まじめな少年の純真さが現れているとは
見なせるように思う。自分の幼稚に無自覚かよほどあつかましければ、的を当てた後に、平気な顔して時頼や将軍の前にやってきているはずだ。例えば8歳未満で小笠懸を行った源頼家の方は、おだてられてその気になったのか、その後射芸にみがきをかけ、狩場で獲物を得るほどに上達したが、政治的にはわがまま勝手な人物として放逐され、暗殺されてしまうのとは
、まるで反対の態度といえる。
考えてみれば、時頼やその祖父泰時が自らに課している君子像というのは、公平無私にひたすら国のため、庶民のために尽くしぬく人間で、ひたすらな努力こそが第一、スタンドプレーなどは必要としないのだ。親馬鹿もあったのか、息子に晴れ舞台を踏ませたかった時頼も、かえって愚直とも言えるような息子の誠実な姿に
、国政に尽くしてきた自分たちの姿を重ね合わせて、心から共感をして思わず出たのが最後の言葉だったのではなかろうか。
「やはり、あいつは我が子、北条の子だ。源氏とは違う・・・。」
以上一つの記事から時宗の姿を求めていくと、そこには英雄でも冷酷無残でも文武両道でもない、誠実でまじめな秀才である普通の人間像が浮かび上がってきた。残念ながら大
モンゴル帝国の侵略を断固阻止した護国の英雄といった、なにやら超人めいた姿はそこにはまったく
見あたらなかった。しかしむしろ、普通の人間でありながら、苦労に努力を重ねて困難な国政に当たり、まさに精魂尽きて34歳で死んでしまう時宗であった方が、私は感銘し尊敬できるのであるが・・・、いかがなものだろうか。
お終い
前のページへ
表紙に戻る
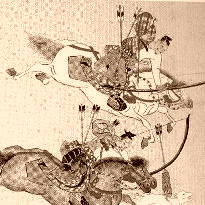 そもそも、わざわざ廃れ気味の小笠懸であるところにも意味がありそうだ。普通の笠懸は馬を疾走させながら、弓手(
馬の進行方向左側)にある的を射ぬく競技であるのに対し、小笠懸は馬手(右側)の至近にある的を射倒す競技だ。自分で馬に乗り、弓をつがえる動作を想像すればわかるが、右利きであれば左真横のものは射やすいが、右側面のものを射ることは出来ない。それでも右側でかろうじて可能なのは、馬の首のすぐ右横から弓の引き手に窮屈な思いをしつつ、矢を放つことが出来るが、この方法を競技化したのが小笠懸なのだ。
そもそも、わざわざ廃れ気味の小笠懸であるところにも意味がありそうだ。普通の笠懸は馬を疾走させながら、弓手(
馬の進行方向左側)にある的を射ぬく競技であるのに対し、小笠懸は馬手(右側)の至近にある的を射倒す競技だ。自分で馬に乗り、弓をつがえる動作を想像すればわかるが、右利きであれば左真横のものは射やすいが、右側面のものを射ることは出来ない。それでも右側でかろうじて可能なのは、馬の首のすぐ右横から弓の引き手に窮屈な思いをしつつ、矢を放つことが出来るが、この方法を競技化したのが小笠懸なのだ。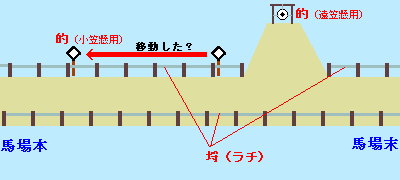 通常の笠懸(遠笠懸)は図のような舞台設定で行われる。馬場元から馬場末にかけて馬を疾走させ、弓手(左側)の中ほどの埒(ラチ)を開いて十数メ―トル離れたところに設置した的を射る。これに対して小笠懸は、馬場末から馬を逆走させつつ、埒際に低く立てた的を前のめり気味に射るものであるという(『国史大辞典』「笠懸」の項による)。
通常の笠懸(遠笠懸)は図のような舞台設定で行われる。馬場元から馬場末にかけて馬を疾走させ、弓手(左側)の中ほどの埒(ラチ)を開いて十数メ―トル離れたところに設置した的を射る。これに対して小笠懸は、馬場末から馬を逆走させつつ、埒際に低く立てた的を前のめり気味に射るものであるという(『国史大辞典』「笠懸」の項による)。