前ふりは長いが、答えは簡単。当の源家が頼朝と二人の息子であっさり断絶してしまったからだ。これでは源家が存在して始めて成り立つ由緒を主張しても仕方がないではないか。
1219年、頼朝の次男の実朝が暗殺されると(彼は北条氏に暗殺されたと考える人がいるが、当時の状況では彼の急死は北条氏に何の得にもなっていない)、北条氏は皇族を将軍に迎えようとしたが、結局は後鳥羽上皇に拒否されて、摂関家で親幕府派であった九条道家の息子、三寅という幼児(2歳未満)を鎌倉に連れてきて将軍に据えることになる。
三寅の母は頼朝の姉の孫娘なので、源家に縁がないわけでもない。そこでこの点を強調したがる人もいるが、実をいうと、縁があろうとなかろうと大した意味はなかった。なぜなら実朝の生前から後鳥羽の息子を養子にする話は進んでおり(当然源家とは縁のない存在)、おそらくその皇子を頼朝と政子の長男頼家の遺児で、政子に養育されていたらしい女の子「竹の御所」(叔父にあたる実朝の養子扱いとなっている)と結婚させて、頼朝と政子直系の源家を存続しようというのが、政子以下北条氏の目論見であった
ようなのだ。つまり北条氏としては婿にするのになるべく高貴な人間を望んだまでで、頼朝との血縁は考慮していなかったのだ。たまたま実朝の死によって後鳥羽が幕府に不信感を持ち、皇子の養子話を撤回してしまったため、スペアとして皇族の次に高貴な摂関家の三寅を連れかえった程度の話なのである。
このあたりの経過を、従来の研究者たちは後に北条氏が専権を振うのに目を奪われて、実朝が邪魔になったので暗殺した後のことを考え、生前から養子話を進めていたとか、子供の方が言いなりになるから都合が良いので三寅となったなどとしているが、はっきり言って見当違いである。本来なら、実朝が暗殺された1219年、1202年生まれの竹の御所は17歳、当時であれば結婚適齢期で、養子となるはずだった後鳥羽の皇子雅成親王(六条宮1200年生まれ)や頼仁親王(冷泉宮1201年生まれ、この人は実朝の正室の甥でもある)と年齢的に非常につりあいが取れており、実に似合いの縁談だったのである。ところが突発的に実朝が暗殺れ、後鳥羽が倒幕を志して承久の乱を起こし、皇子たちも連座して追放処分となってしまったために実現できなくなってしまった
だけである。
結局、承久の乱では、養子予定者だった親王を含めて軒並み皇族は追放され、天皇家を継ぐ者すらいなくなる始末となり(誰もいないので天皇となっていない守貞親王の子供を天皇とする異例の処置となる)、竹の御所に見合う(と北条氏が考える)身分の相手は、スペアとして連れかえった親子ほど年下の三寅しか残らない状況となっ
てしまったのだ。これは、まったく、不幸なことと言わねばならない。
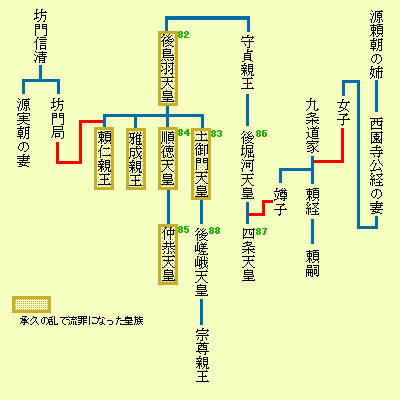 その後、1230年に二人は結婚するのだが、花嫁28歳、花婿13歳であった。何か、ギリギリと歯噛みをしながら三寅の成長を待っていた北条氏の思いが、強烈に伝わってくる。とにかく政子以下北条氏(執権は泰時)としてみれば、竹の御所に男の子が生まれれば、源家を再興させる心積もり、さらにその子に北条氏の娘を嫁がせて・・・くらいの腹づもりをしていたに相違ないのだ。
その後、1230年に二人は結婚するのだが、花嫁28歳、花婿13歳であった。何か、ギリギリと歯噛みをしながら三寅の成長を待っていた北条氏の思いが、強烈に伝わってくる。とにかく政子以下北条氏(執権は泰時)としてみれば、竹の御所に男の子が生まれれば、源家を再興させる心積もり、さらにその子に北条氏の娘を嫁がせて・・・くらいの腹づもりをしていたに相違ないのだ。
そして有難いことに決定的な年齢差とは無関係に夫婦仲は良かったようだ。しばらくするとまず女の子が生まれ、1234年に再び懐妊する。ところが、何と難産のために肝心の竹の御所は亡くなってしまう。当時としては高齢出産で、負担が大きかったのかもしれない。
竹の御所個人を考えた時、まったく悲惨な話である。
残された姫は北条氏によって大切に養育されていたようだが、その竹の御所の忘れ形見も1235年7月以降となると記録がない。存命なら竹の御所と同じ役割を期待された
可能性が高いから、早い段階で亡くなってしまったのではなかろうか。
この名も知られぬ姫の死により、完全に頼朝と政子の源家は断絶し、源家の外戚家としての北条家の由緒も、ほとんど意味をなさないものとなってしまうのである。
残されたのは成人した婿の三寅、九条頼経。その時の北条氏の当主は政子の甥の泰時。さすが穏健な名君として名高い彼は、もはや北条氏のためには意味があるとも思えない将軍頼経をそのままにしておく。そして北条氏が他氏に優越する根拠は何にもない状態ながら(将軍と何のつながりもない)、泰時個人の政治力で求心力を保つ(合議制を用いることで不満をなくす)。
ただ、泰時本人が頼朝の隠し子だとのうわさもあったようなので、いざとなれば自ら将軍家を簒奪する気持ちもあったかもしれない(意図的にうわさを流すのは簡単)。しかし、まだ三浦氏のような有力なライバル(彼らは先祖代々源氏嫡流の家来であったことを殊の外誇りにする)もあったので、露骨な簒奪を控え、細い糸のような偶然のつながりながら、源
家に縁のある頼経を戴きつづけるのを得策としたのだろう。この辺はうわさに違わず実に賢明な人物と言えよう。
しかし、個人的に力量も実績もある泰時が1242年に死んでしまうと、北条氏の立場はたちまち怪しくなる。跡を継いだのは孫の経時でまだ若く、カリスマ的な求心力は持ちえない。反対に将軍頼経は壮年となっている。彼は摂関家の家柄で、頼朝とも縁続きという血統的な背景を持ち(政子の子孫が絶えてしまってからこの些細な血縁が意味を持ちはじめたのではないかと思う)、現に幕府の主催者であるはずの将軍
の地位にあり(幕府は本来は派遣軍の占領統治組織みたいなものなので、1945年日本が連合軍に負けた時のGHQが幕府で、マッカーサーが将軍と考えて間違いない)、さらに実父の九条道家は当時の京都朝廷
において最有力人物であった。外戚でも何でもなく、何となく実力で将軍の補佐役である執権をしている若僧の北条経時より、よほど求心力を持っても不思議ではない。
危機を感じた執権経時は、1244年難癖をつけて、とにもかくにも頼経を隠居させてしまい、その子供の頼嗣(5歳未満)を将軍とする。幼児なら少なくとも主体的に事を起こす危険はない。そして翌年にはすばやく妹(檜皮姫16歳)を
この幼児の新将軍に嫁がせる。『吾妻鏡』の寛元3年7月26日条には、この時のことを披露もせず「密儀」でことを運ぶとしている。式も挙げずに押しかけ女房さながらの強引さで、反対が出る前に既成事実を作ってしまおうとの魂胆がうかがわれ
よう。無理矢理年齢のつりあわない政略結婚を再びこりずに行なったわけだが、ともあれ将軍家の御台所(正妻)の実家という立場に北条氏を復帰させることが出来た。
ところが自らの正統性を確保したのもつかの間、1246年執権の経時が死んでしまう。大きく動揺する場面だが、跡を継いだ弟の時頼は兄以上の相当なやり手で、彼は即座に北条氏内部の対抗勢力(名越氏)を武力制圧して足元を固め、さらにそれに連座したとして前将軍(「大御所」と呼ばれていた)の頼経を京都に追放する。実に手際が良いが、
現将軍の義兄という立場(御台所の一族、つまり頼朝にとっての北条氏と同じ立場)にあればこそ可能となった強硬手段ともいえる。
この辺の政治史は食うか食われるか、血なまぐさいドロドロの闘争であり、情勢はくるくると変わる。そして誰も注目しないが、実は大きな意味を持つ一人の女性の死が
あった。1247年5月、「御台所」となっていた檜皮姫が死んでしまったのである。
※ 前年の経時とこの年の檜皮姫、兄妹の相次ぐ死に暗殺だと忍者映画さながらに簡単に考える人がいるかも知れないが、いちいちそんなことを考えなくとも当時は疫病その他で若死は珍しくない。第一、非権力者の側が権力者を簡単に毒殺なり暗殺出来るくらいなら苦労しない。
妹の檜皮姫の死によって執権時頼の外戚一族という正当性はまたも簡単に崩壊する。しかしここでも時頼は素早かった。母松下禅尼の実家安達氏と協力して、不満分子の三浦氏を挑発して一気に武力制圧してしまう。源家の譜代の家来としての家柄にとりわけ誇りを持つ三浦氏は、頼朝の墓所に建つ堂内で族滅する。彼らは自己の滅亡を源
家将軍の滅亡と見なしていたので、わざわざ頼朝の墓前に集まって死んでいったに相違ない。
その三浦氏の認識は間違っていなかった。反対勢力を一掃した時頼は、もはや自己の正当性を将軍の頼嗣には求めなかった。妹の檜皮姫の死によって、彼は将軍の外戚といった協調路線を捨て、独自路線を明確に指向し始めたのである。その動向は見ようによってはかなり露骨なものであった。1251年5月彼自身の正妻が男子(時宗)を産むと、翌年2月に京都政界の実力者九条道家が死に、3月には新将軍として宗尊親王が京都から鎌倉へ下向をはじめ、ご用済みとばかりに将軍頼嗣は京都に追い払われる。もはや細い糸の源家の記憶、ひいてはそれなくしては成り立ちえない自らの家の由緒(源家の外戚)を破棄したも同然である。そして新たに推戴することになった宗尊親王に嫁を差し出したりもしない(形式的に親王を自分の養子分にしてしまう)。つまり、他
の存在があってはじめて権威づけられる類の由緒を捨て、はっきり独立した権威として北条氏を位置付けようと思いきったものと考えられよう。外戚の危うさが身にしみた結果ではないかと思う。
※ 将軍の交代に反対するはずの道家の死のタイミングも良すぎると見る向きもあるが、彼が生きていようと将軍交代は進められていたに相違ない。なぜなら道家は実力者だったのは幕府とのパイプがあったからで、幕府に見放されれば勢力を失うだけであり、実際彼の勢威は外孫の四条天皇が夭折(12歳)された時点で失われていた(四条天皇の後継者として、道家は外孫でもある順徳天皇の子を望んだようだが、幕府は土御門天皇の皇子を即位させた)。失意の中でさらに彼の意向を無視して進む将軍のすげ替え(彼にしてみれば、孫の頼嗣が将軍をクビになる)を前に、高齢の彼はくやしさで憤死したと考えた方が良いと思う。さぞ無念であったろう。
さらに1256年8月に九条頼経、9月に頼嗣が相次いで亡くなっているが、これも病死に過ぎない。何の力もない前将軍など、豪腕の時頼が無理して殺す必要はない。第一この時期は京都でも鎌倉でも麻疹(はしか)が流行って大変なことになっていた。時頼自身も宗尊親王も罹患し、二人は助かったものの、時頼の娘も京都では後嵯峨上皇の妹も亡くなられている。九条家の二人の死だけを特別に考える方がおかしい。
※ 『大河』は時宗の母を三浦氏と共に滅んだ毛利季光の娘とし、1247年に北条重時の養女として嫁いだことにしているが、そのような事実は見出せない。明らかなのは、時頼が執権になる以前の1239年11月2日に毛利季光の娘と結婚していたが(時宗誕生の8年前であることに注意、なお花婿の時頼は当時12歳)、後に時宗の母として明記されているのは「重時娘」だということである。この辺の詳細は
『吾妻鏡』に特別記載がないので研究者の中にすら混同が見られるが、時頼が三浦氏を滅ぼした際に、父親の季光が娘の婚家ではなく妻の実家の三浦氏と行動を共にしているのを見ると、1247年時点ではすでに時頼の妻となっていた娘は亡くなっていた可能性が
高い。また存命であっても、いまだ子供に恵まれなかったと思われる彼女は、少なくとも父親の死亡後正妻の地位を失い、かわって重時の娘が正妻に納まって時宗以下を産んだと考えるのが常識的な判断であろう。重時が時頼の連署(執権の補佐役)を勤めたり、重時の息子の長時が時頼が出家した後の執権となったりするのは、その緊密な婚姻関係に基づいて考えなければ理解しがたい
のだ。
この点は、前ページに挙げた系図で、北条得宗家、安達家、北条重時家(赤橋流)の相互に入り組んだ関係を参照頂きたい。
独自の権威を北条氏に付随させるにあたって時頼が用いた手段は、まず自らの嫡流を得宗と呼称するところにもあったかもしれない。得宗とは時頼にとっては曽祖父にあたる義時の法名であり、つまりは義時の嫡流を誇示している呼称と言える。つまり義時に自らの正統性の由緒を見ていることを表明しているわけである。義時は現在
では、影が薄く、知る人も少ないかもしれないが、承久の乱で京都の朝廷軍を打ち破り、本来国の最高権力者である「治天の君」後鳥羽上皇を島流しにし、仲恭天皇から皇位を剥奪するという、まさに前代未聞、驚天動地の処分を断行し、幕府権力を朝廷をしのぐものにした大人物だったのである。
承久の乱の結果、義時のおかげで帝位についたのが後堀河天皇なら、その系統が絶えて、義時の嫡男泰時のおかげで帝位についたのが後嵯峨天皇である。その後嵯峨の子供
である宗尊親王を将軍とするにあたって、自らを得宗と誇示するのは意味深長であろう。時頼にしてみれば、自分たち北条氏は帝位(権威)も左右できる特別な権力者の家系であると位置付けたかったのではなかろうか。
しかし義時を由緒とするのには弊害もある。彼は朝廷での位は低いままだったので、その由緒を強調する以上、子孫もそれに準じなければならない。位階は五位に止まり、その点で他の武士たちと大差はないので、差別化が難しくなってしまう。
そこで違った側面で他の氏族と差別化を試みる必要があり、時頼はすでに消滅した源家の権威を北条氏に付随させることを思いついたようだ。例えば源家は頼義以来弓の名手ということになってい
た家柄で、頼朝も百発百中だったとされ、幼児の息子頼家に小笠懸を行なわせ「その射芸の才能は天性のものだ」などと家来たちに言わせているのだが、全くそれをマネして、衆人環視のもとで息子の時宗に小笠懸を行なわせたりする。
これは、弓が得意=源家を継ぐ者といったイメージを演出しようという極めて政治的な目的があったものと思われる。
※ なお武士の棟梁=源氏=代々弓の達人、ということ自体がイメージに過ぎず、そんなもののために源頼朝や北条時頼といった
日本史上でも稀に見る政治家が苦心するのは、現代人にしてみれば奇妙な話だが、当時は由緒というイメージに現実を合わせなければ済まない時代なのである。例えば、頼朝は義経をかくまったと難癖をつけて奥州藤原氏を数十万!の大軍で踏み潰した際に、100年以上前の前九年の役の際に先祖の頼義が歩んだ日程に無理やり合わせて行動していることが知られているように、彼は明らかに頼義に自分を重ねている。
何しろ直方流平氏の娘を妻にしているという共通項があるのだから、頼朝のこの自己認識は一面において当然であろう。そして、自らが「頼義」なら、息子は「義家」でなければならず、元服すれば迷わず『家』という字をつけて頼家と名乗らせ
ている。「義家」であれば、人並みはずれて弓の名人でなければならないので、小笠懸をしたり、狩りで鹿を仕留めるとやたらに喜んだりもしている(政子にはたしなめられる)。
血統的由緒のない時頼は、そのイメージのみをを取り込もうとしたのである。
 さらに、豪腕ながら芸も細かい時頼は、独立した権威ある家柄ともなれば、北条氏が元々源家の外戚家であったように、嫁を供給する特定の家も用意せねばならないと考えたようだ。それが自分の母の実家であった安達氏である。嫡男時宗が元服すれば早速に安達氏の娘を迎える。1285年の霜月騒動で安達氏の本家は滅んでしまうが、その後
時宗の子北条貞時の妻も安達一族の出身者を迎え高時を生むように、この伝統は1333年に滅亡するまで続けられる。
さらに、豪腕ながら芸も細かい時頼は、独立した権威ある家柄ともなれば、北条氏が元々源家の外戚家であったように、嫁を供給する特定の家も用意せねばならないと考えたようだ。それが自分の母の実家であった安達氏である。嫡男時宗が元服すれば早速に安達氏の娘を迎える。1285年の霜月騒動で安達氏の本家は滅んでしまうが、その後
時宗の子北条貞時の妻も安達一族の出身者を迎え高時を生むように、この伝統は1333年に滅亡するまで続けられる。
なぜ安達氏なのか。一般に信じられているような、安達氏が本来将軍家の家来である御家人身分を代表する家だったので、それとのバランス上の処置といったもの
とは見なせない。何しろ安達氏と言うのは、源家の譜代の家臣としての由緒をもつ家柄であったかはわからない存在で、初代として登場する盛長は妻の母である比企尼が頼朝の乳母(養育係)だったので、その指示で頼朝の流人時代から家臣となっていたに過ぎない。つまり、源家の譜代の存在ではな
く、本来的な御家人を代表する存在とは見なすのは適当ではないのである(ここでは御家人=幕府に属する武士階級と広義には考えていない。あくまでも由緒の中で源家とつながりを持つ存在、つまり絶対的に家来でなければならない者を御家人と見なしている)。
さらに盛長の息子の景盛などは政子に命を助けてもらった経歴がある。何でも、景盛の美人の妾を源家二代将軍の頼家が景盛を出張させた留守に掠め取ってしまい、それに景盛が不平を言うのを謀反として処分しようとしたのを、政子が身体をはって止めたというのである。これでは無茶苦茶な将軍家よりも政子を頼りにしたはずで、政子の家臣となれば、源家の御家人と言うより
、もとから北条氏のシンパと考えた方がより事実に近い存在といえよう。実際、景盛は北条氏の嫡男時氏に娘を嫁がせ、両氏は一蓮托生の密接な関係となる。北条氏はそのシンパを外戚家に位置付けたわけで、別に御家人身分の代表者として安達氏を抱き込もうとしたわけではないのである。母の実家でもあり、敵対する根拠となりうる由緒もないため、パートナーとして適当と考えられたのではなかろうか。
この特定の外戚家を設定することは、室町時代の足利将軍家にも受け継がれ、日野氏がその位置につく。ある程度婚姻氏族を絞っておいた方が、一々外戚となった家が入れ替わって権力バランスが崩れることもなく、政権の安定がはかれるという面があるのかもしれない。
時頼としては、親王将軍を迎え、将軍家を天皇家に準じる存在に格上げした上で、その下で武家の棟梁として帝位すら左右する得宗家が武家の棟梁としての源家のイメージを吸収して
存在するといった構想のもとに、行動しつつあったように思われる。しかし息子の時宗は形式的な源家化の必要性を理解しなかったし(小笠懸では途中で帰ってしまう)、時頼もその態度にかえって北条氏の人間として共感してしまう始末で(この辺の解釈は『北条時宗は弓が嫌い』を参照のこと)、さらに
時頼自身既成事実を積み上げることもなく若死にしてしまう。
残されたのは、源家の外戚家という本来の由緒を消失し、得宗家という独自の由緒を創出しようとした痕跡(安達氏を外戚にする)だけであり、朝廷での位は伝統的な五位(県知事クラス)に止まり、宮将軍という飾りを戴きながら執権としての実力のみで政権を運営しつづけねばならない北条氏の姿であった。
そして子供の時宗も孫の貞時も曾孫の高時もその位置付けを改めようとはしていない(時宗は存命中は蒙古襲来で奔走しなければならず、結局早死にしてしまったので、父の得宗家の独自権威化といったビジョンを肉付する暇もなく、それを子孫に伝える事も出来なかったのかもしれない)。もっとも、得宗なる者が天下第一の実力者である事は紛れもなく、何となくうやむやのままでも問題はなかった。
しかし、義時を始祖とする北条氏の立場は1333年に滅亡してしまう時点で「義時ってなんだ。在庁の時政のせがれじゃないか」と言われてしまえば、一気に崩壊するタイプのものでしかな
くなっていたのだった。何しろ義時が帝位を左右したのは武力による実力で、それ自体を正当化するような由緒は存在しない。むしろ、天皇家に刃向かった逆賊の家というレッテルをはられかねない。
本来の源家の外戚家という由緒は放棄してしまい、源家のイメージも継承できなかった。結局北条氏は自己の実力以外に権威を裏付けるものがなくなり、天皇家=権威というような、実力とは無関係に何となく存在する伝統的権威となるためにはまったく時間がたりず、何とも中途半端で得体の知れない一族と見なされてしまう結果となったのである。得宗などと威張ってみても、北条氏内部の総本家という意味を持つくらいにしか理解されないのだ。これは悲劇というべきではなかろうか。
それにしても、「いくら何でも、馬の骨扱いはひどいじゃないか!」、北鎌倉のあじさい寺(明月院)で眠る時頼の憤慨する声が聞こえてくるのは気のせいだろうか。
お終い
前のページへ
表紙に戻る
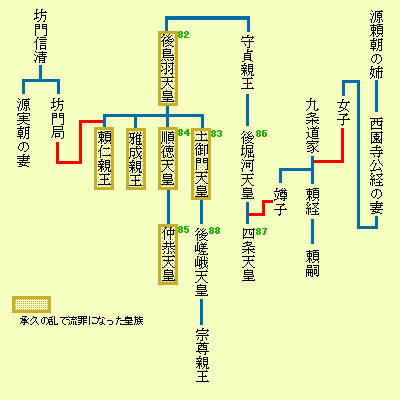 その後、1230年に二人は結婚するのだが、花嫁28歳、花婿13歳であった。何か、ギリギリと歯噛みをしながら三寅の成長を待っていた北条氏の思いが、強烈に伝わってくる。とにかく政子以下北条氏(執権は泰時)としてみれば、竹の御所に男の子が生まれれば、源家を再興させる心積もり、さらにその子に北条氏の娘を嫁がせて・・・くらいの腹づもりをしていたに相違ないのだ。
その後、1230年に二人は結婚するのだが、花嫁28歳、花婿13歳であった。何か、ギリギリと歯噛みをしながら三寅の成長を待っていた北条氏の思いが、強烈に伝わってくる。とにかく政子以下北条氏(執権は泰時)としてみれば、竹の御所に男の子が生まれれば、源家を再興させる心積もり、さらにその子に北条氏の娘を嫁がせて・・・くらいの腹づもりをしていたに相違ないのだ。 さらに、豪腕ながら芸も細かい時頼は、独立した権威ある家柄ともなれば、北条氏が元々源家の外戚家であったように、嫁を供給する特定の家も用意せねばならないと考えたようだ。それが自分の母の実家であった安達氏である。嫡男時宗が元服すれば早速に安達氏の娘を迎える。1285年の霜月騒動で安達氏の本家は滅んでしまうが、その後
時宗の子北条貞時の妻も安達一族の出身者を迎え高時を生むように、この伝統は1333年に滅亡するまで続けられる。
さらに、豪腕ながら芸も細かい時頼は、独立した権威ある家柄ともなれば、北条氏が元々源家の外戚家であったように、嫁を供給する特定の家も用意せねばならないと考えたようだ。それが自分の母の実家であった安達氏である。嫡男時宗が元服すれば早速に安達氏の娘を迎える。1285年の霜月騒動で安達氏の本家は滅んでしまうが、その後
時宗の子北条貞時の妻も安達一族の出身者を迎え高時を生むように、この伝統は1333年に滅亡するまで続けられる。